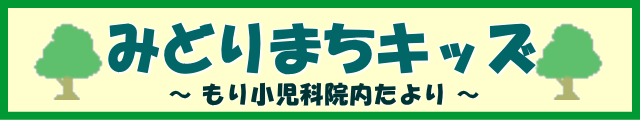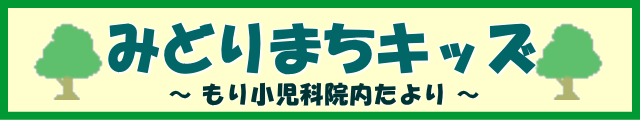| 【乳幼児のお子さんに坐薬を勧める理由】 |
| ◆ |
いつでも使用できる
坐薬はぐったりしている、食欲がない、吐きやすい、眠っている時等にも使用できます。 |
| ◆ |
使いやすい
上手にお薬が飲めない、お薬の味が苦手なお子さんにも使用することができます。
細粒のカロナールは甘くコーティングされていますが後で少し苦味がでます。小さいお子さんは本能的に苦味を嫌うため、うまく飲んでくれなかったり嫌がったりします。
坐薬は入れた直後に出てしまった場合、形が残っていれば再度挿入することができます。
飲み薬は吐いてしまうと6時間は使えません。 |
| ◆ |
使用期限が長い
坐薬(アンヒバ)は製造後5年まで使えます。
余ったら冷蔵庫で保管しておくと次回の発熱時にも使えるお守りになります。 |
| しかし坐薬は「痛い」「怖い」と嫌がるお子さんも多く、入れる側のお父さん・お母さんにとっても「使うのが大変」「苦手」だと思われている方も多いのではないでしょうか。 |
| 【坐薬をスムーズに入れるポイント】 |
| ◆ |
発熱(38.5℃以上)が続きぐったりしているときに使いましょう。
解熱剤はそれ自体に病気を治す効果はなく一時的に発熱の辛さを軽くするものです。
発熱があっても水分や睡眠がとれていたり暴れるほど坐薬を嫌がる元気があるなら急いで解熱させる必要はありません。
|
| ◆ |
坐薬が入りやすい体勢をしっかりとりましょう。(肛門がしっかり見える状態)
乳児⇒仰向きにし、両足を持ち上げその足をお腹にしっかりくっつけます。
幼児⇒横向きにし、両膝を曲げお尻を後ろに突き出します。 |
| ◆ |
坐薬は滑りやすくしておきましょう。
先端を手で温めたりベビーオイルをつけます。 |
| ◆ |
入れる時はさりげなく
お父さんやお母さんが坐薬をいれることに不安を感じたり戸惑ったりすると、お子さんはお父さんお母さんの感情に敏感なので不安や恐怖心を感じて嫌がることがあります。 |
| |
「どうやって入れるんだろう」「うまく入れられるかな」と不安に感じている方は、ご遠慮なく看護師までお声掛けください。
また診察室前の廊下に設置してあるパンフレット「解熱剤の使い方」や裏面の「解熱剤(坐薬)について」もご参考ください。 |
| 3歳頃までは薬に対して最も抵抗感がある時期で飲み薬は吐き出したり上手に飲めなかったりします。飲み薬が上手に飲めるようになる3歳頃までは坐薬を使ってみてはいかがでしょうか? |